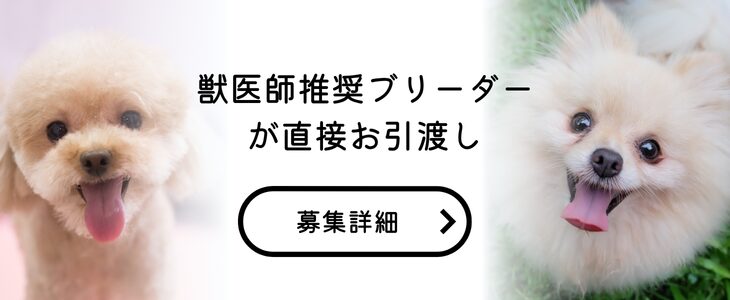過去、このようなお問い合わせがありました。
「今年、愛犬が突然死してしまい辛く寂しい思いをしています。私は定年退職している一人暮らしです。ですので愛犬と過ごす毎日が幸せでした。
もう一度わんこと生活したいと思い、保護施設にも何度か足を運びましたが、単身者、かつ年齢の理由からは応募すら叶わず。
途方に暮れていたところ、亡くなった愛犬と同い年で募集されてるワンちゃんを知り、一緒に幸せな時間を過ごせたら…と思い、問い合わせをいたしました。
私でも、お迎えは可能でしょうか?」(内容を一部変更しています。)
保護犬の厳しい里親譲渡条件
60歳以上だからこそ、ご自身の年齢を考慮し、子犬ではなく成犬を望む声は多くあります。
しかし、成犬をお迎えできる場所はそう多くはありません。
成犬と家族になる場合、保護犬(一般家庭の飼育放棄・繁殖引退犬・野良の犬)が選択肢に入りますが、保護犬は譲渡の条件が厳しく設定されています。
「二度とおうちが無くらないように」
「審査に時間をかけられない」
などの理由から、下記のような方は応募すら難しいというのが現実です。
里親になれないご家庭の一覧
60歳以上、学生、単身者、同棲、事実婚、妊婦、小さいお子さんがいる夫婦、4時間以上の留守、ペット飼育経験無し、賃貸住み(ペット可でもNG)、頼れる親族が近くにいない、先住犬・猫がいる など。
しかし、当サイト ペットの最後のおうちでは、シニア世代だからこそ、事情のあるワンちゃんを迎え入れる「心の余裕がある」と考えています。
そもそも、今の60代はとっても若々しい!!
シニア世代に犬を託すメリット
・我が子のように「時間」と「お金」をかけてもらえる。
・日中もお世話をしてもらえる。
・家庭環境(結婚・離婚・引っ越し)が変わらない可能性が高い。
・子育てや仕事を終え、心や生活にゆとりがある。
・お子さんも成人している場合が多く、もしもの時にお願いできる。
これらの理由から、ペットの最後のおうちではシニア世代の方へのお引渡しも行っています。
募集中のワンちゃん・ネコちゃんたちはこちら

ペットの最後のおうちとは?
ペットの最後のおうちで募集しているワンちゃんは、保護犬ではありません。
ブリーダーが直接譲渡する、繁殖引退犬やハンデのあるワンちゃんです。
ワンちゃんを迎え入れたいという方と、ワンちゃんをブリーダー自身の手で次の家族に託したいという双方の想いを繋げる仕組みです。
★ペットの最後のおうちの犬の譲渡条件
譲渡条件は、犬の性格や年齢に応じて決めています。
そのため、一般的に里親候補としてお断りされやすい単身者の方、65歳以上の方、同棲、事実婚、お子様のいるご家庭、お仕事をされている方、先住動物がいらっしゃるご家庭でもご応募いただけます。
詳細は、個々の募集要項に記載しています。
ご家族の同意を得たうえでお問い合わせください。
例)犬が苦手なワンちゃんの譲渡条件は・・・
先住動物はなし、もしくは1頭まで。などが譲渡条件となります。
ブリーダーが直接引き渡しを行うことで、里親さんにはこれらが提供できるようになります。
✔ これまでの出産回数
✔ 病歴・治療歴
✔ 性格や癖、特徴、好きな遊び
✔ ブリーダーの飼育環境
✔ 生まれた子供たちとそのお迎えした家族(SNSで繋がることもできます)
✔ 正確な誕生日
✔ お迎え後の相談
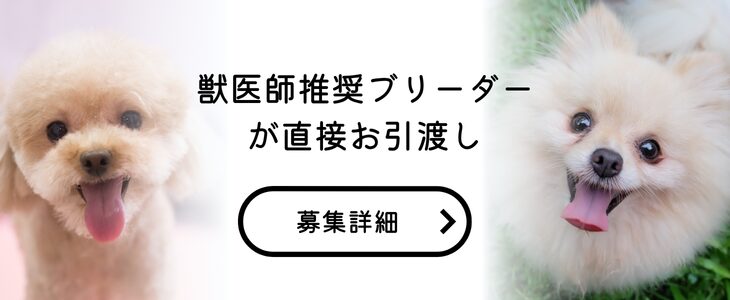
繁殖引退犬とは
ポメラニアンやトイプードルなどの純血種のワンちゃんは、ブリーダーの手助けによってその種の保管が行われています。そして、ブリーダーの元で生まれた子犬たちが、ペットショップやブリーダーサイトを通じて一般家庭に旅立ち、家族として暮らしています。
その育児を終えた親たちのことを、一般的に「繁殖引退犬」「ブリード卒業犬」などと呼んでいます。
2021年からブリーダーに対しての法律大きく変わり、飼育頭数や飼育員の人数、飼育場所の広さなどに制限がかかり、親犬の老後までブリーダーが一緒に暮らすことが難しくなりました。
そのため、出産・育児を終えた親たちを、一般家庭へ送り出すブリーダーが増えています。詳細はこちら
ハンデのあるワンちゃんとは
生まれつき障害をもったワンちゃんや、ケガや骨折により、ペットショップやブリーダーサイトでの取り扱いが難しく、家族が見つかりにくいワンちゃんがいます。
当サイトでは、これまで水頭症・口唇口蓋裂・骨折・発達障害(人間でいう自閉症のようなもの)・心臓病など、ハンデのあるワンちゃんを、新しいご家族様へ託してきました。
これらのハンデがあるワンちゃんは、ブリーダーが適切な治療を行った上でしっかりと説明させていただいた上で、お引渡しをしています。
ご縁をいただいたご家族様からのメッセージ
引退犬を迎えた方から
先日愛犬を見送りました。
もう一度ワンライフを、と願うものの、年齢を考えると子犬も保護犬も難しく。
繁殖引退犬をブリーダーが直接譲渡していると知り、かなり遠かったですがお迎えさせていただくことになりました。ブリーダーが数年お世話をしていたこともあって、その犬の個性に特化した生活スタイルを細かく教えていただくことができました。
この子が最後のワンちゃんです。大切に暮らしていきます。
先天性 口唇口蓋裂の子犬を迎えた里親様から
ハンデのある子犬を見放さず、夜間も授乳を続けたとお聞きしました。このような素敵なブリーダーから迎えることができ、また手術も行って頂き、とても感謝しております。
この度はありがとうございました。
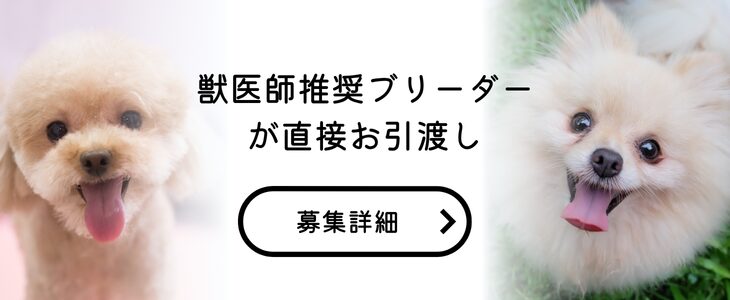
そもそも、60歳以上でも犬を飼えるのか?
基本的に年齢制限はありませんが、以下の点を考慮する必要があります。
- 犬の寿命
犬の平均寿命は大型犬であれば10歳、小型・中型犬は15年ほど。現在里親さんの年齢が60歳の場合、犬が寿命を迎えるころには70代になります。現在は犬の寿命も大幅に伸び、小型犬でも20年は視野に入れましょう。 - 体力と世話
特に子犬や大型犬、狩猟犬、牧羊犬等はエネルギッシュで、しつけや散歩、食事の管理が必要です。特に大型犬や活発な犬種は運動量が多いため、体力や、散歩で引っ張られない握力に自信があるか確認しましょう。 - 万が一の備え
自分が病気や入院になったときに、犬の世話を引き継げる家族や友人がいるか事前に相談しましょう。 - 犬種による育てやすさ
犬種により、吠える量や運動量などに大きな差があります。お迎えする犬種について、専門的なブリーダーから生活について聞くのがいいでしょう。
60歳以上が子犬を迎えるメリット
子犬を飼うことは、シニア世代にとって多くのメリットがあります。
- 生活にハリが出る
毎日散歩をすることで、運動不足が解消され、健康的な生活を送れます。 - 認知症予防になる
犬の世話をすることで、脳を使う機会が増え、認知機能の低下を防ぐ効果が期待できます。 - 癒しと安心感
犬の存在が精神的な支えとなり、ストレスが軽減されると言われています。
成犬ではなく、子犬を迎える場合
60歳以上が子犬を迎える際の注意点
(1) 飼いやすい犬種を選ぶ
子犬の性格や運動量を考慮し、無理のない犬種を選びましょう。おすすめの犬種は以下の通り。
- 小型犬(チワワ、トイプードル、ミニチュアダックスフンドなど)
→ 運動量が少なく、室内飼いに向いている - 穏やかな性格の犬(キャバリア、フレンチブルドッグなど)
→ おとなしく、人懐っこい
(2) しつけに時間をかける
子犬は成犬に比べてしつけが必要です。トイレトレーニングや甘噛みの対策に時間をかける覚悟を持ちましょう。
(3) 経済的な負担を考慮する
子犬の飼育には、以下のような費用がかかります。
- 初期費用(ワクチン、マイクロチップ、トイレ用品など)
- 継続的な費用(フード、健康診断、トリミングなど)
まとめ
60歳以上でも犬を飼うことは可能です。
そして、シニア世代の多くはご自身の年齢を顧慮し、成犬を視野に保護犬を探されます。
しかし、保護犬の里親条件は厳しく、簡単にお迎えできることはありません。
ペットの最後のおうちでは、ワンちゃんと暮らす日々の豊かさを提供するために、里親さんと犬の個性を考慮し譲渡を行っています。